Artist in Residence Programアーティスト・イン・レジデンスプログラム
2015 レジデント・アーティスト
今年は、海外88か国・地域から599件の応募がありました。厳選なる審査の結果、ティモテウス・アンガワン・クスノ(インドネシア)、ステファニー・ビックフォード=スミス(英国)、エドゥアルド・カシューシュ(南アフリカ)を選出しました。3名のアーティストは、8月18日から12月5日までの110日間、茨城県守谷市のアーカススタジオで滞在制作を行います。
審査は、飯田志保子氏(2015年度ゲストキュレーター/キュレーター/東京藝術大学美術学部先端芸術表現科准教授)、南條史生氏(アーカスプロジェクトアドバイザー/森美術館館長)、アーカスプロジェクト実行委員会の協議のもと行いました。
2015年度の選考結果について
既に国際的な活動歴が豊富な中堅アーティストから大学を卒業・修了したばかりの若手作家まで、世界中のさまざまな地域から計599件の応募があった。アフリカ、南米、中東からの応募も散見されたことから、近年の国際的なアートシーンの潮流がレジデンスにも反映していることが窺える。応募者層の厚さから、アーカスプロジェクトの20年以上に及ぶ実績と評判が実感される充実した選考となった。
なかにはダイナミックな大型彫刻や、守谷全域での展開が期待されるサウンド作品の提案、ステレオタイプな日本の文化表象に捉われない独自のリサーチを経たうえでのプランなど、実現が楽しみなアーティストが複数いたため、ファイナリストの絞り込みは悩ましい限りだった。最終的にはアーカスプロジェクトの目的と特徴を鑑み、展示を前提とした作品の完成より、守谷での滞在が将来的な制作の糧になるであろうと思われる提案のアーティストを選出した。結果、近作で自身の表現言語とそれに適切なリサーチ方法を獲得した段階で、高い将来性が期待される若手アーティスト3名を選出した。
飯田志保子(2015年度ゲストキュレーター)
ティモテウス・アンガワン・クスノTimoteus Anggawan Kusno
インドネシア

1989年インドネシア・ジョグジャカルタ生まれ、在住。2012年ガジャ・マダ大学(ジョグジャカルタ)政治・社会学部コミュニケーション学科にてメディア・スタディーズの学士号取得。制作にはドローイング、グラフィック・デザイン、写真、映像、文学作品の執筆や編集と多岐にわたる技法を用いる。2014年にはクダイ・クブン・フォーラムで初個展「Ethnography Exhibition by Center for Tanah Runcuk Studies: Memoar Tanah Runchuk」(クダイ・クブン・フォーラム、ジョグジャカルタ、2014)を開催。植民地時代から伝わる実存不確かな領土をめぐるフィクショナルな研究を構築し、地域住民や木工、版画、製本、皮細工職人とのコラボレーションによって、そのストーリーに血肉を与える作品群を創出した。その他主な展覧会に「Liminal」(チュムティ・アートハウス、ジョグジャカルタ、2015)、「Les Tonnerres de Brest 2012」(ブレスト、フランス、2012)などがある。
活動の様子

Interview and shooting with Enomoto Miyoko and Katsuo at the Enomoto house

Work in progress at the studio

Edit the interview film

Studio visit by the guest curator Iida Shihoko
オープンスタジオ

LOST AND FOUND & LOST AND KARAOKE CLUB in LFLW (17:30–19:00)

Instruction of participatory workshop at FORGETTING & REMEMBERING CLUB in LFLW (13:00 –16:00)

Open Studios: Collection of research materials and drawings by the artist
アーティスト・ステイトメント
《何を覚えていたか忘れた》
レジデンスプログラムの期間中、私は人々から物語、記憶、また秘められた質問を「Lost and Found and Lost and What Department (LFLW : 失くして見つけて失くしてそれからどうなる課)」を通じて集めてきました。LFLWは、私のスタジオ内に設立された架空の機関です。私はここで集めた物語に手を加え、参加可能なインスタレーションとして疑問を掲げます。LFLWはオープンスタジオ会期中にオープンしています。同じ部屋を時間帯で分けて活動展開することで、「忘れる事」、「思い出す事」に区切りをつけ、対比を浮き上がらせます。昼間にスタジオは「フォゲッティング&リメンバリングクラブ」となり、夜には「ロスト アンド ファウンド&ロスト アンド カラオケクラブ」へと替わります。
昼間だけオープンしている「フォゲッティング&リメンバリングクラブ」では、スタジオで用意している材料を使って参加者自身の物語を共有することができます。そして、日が沈んでからは「ロスト アンド ファウンド&ロスト アンド カラオケクラブ」となり、どなたでもご参加いただけるステージを用意しています。オープンスタジオ最終日には、この「失くして見つけて失くしてそれからどうなる課:LFLW」の「ロスト アンド ファウンド&ロスト アンド カラオケクラブ」にてDJパーティーを行う予定です。
この制作は「Remembering and Forgetting as Social Institution」(1990年)について議論したジョン・ショッター(John Shotter)への応答です。一方で、この制作は過去2年間に私が取り組んできた「歴史上の架空の物語」を展開する既存の方法へ挑戦する実験でもあります。過去に私は、「架空の物語」を歴史に加えることで、語られることのない集合的な記憶を記録する実験を試みてきました。今回の滞在では、実際に語られた記憶を集める方法を優先的に行い、仮説(またはフィクションと思われるもの)を通して課題を投げかけることを試しています。
選考理由
想像上の異形の動物を描いたドローイングと彫刻が非常に魅力的だった。それらが単にアーティスト個人のファンタジーに由来するものではなく、植民地時代の文献資料や工芸品や遺物のリサーチを基に創造されたということ、また実存不確かな失われたテリトリーを成す一部であるという設定が興味深い。書かれたもの、フォークロア、民話といった不確かな物語は、クスノの民族誌学者のようなアプローチによって、有形の作品として現代に顕在化される。そこには史実からこぼれ落ちたものに目を向けてオルタナティヴ・ヒストリーを構築しようとする姿勢が感じられ、アーカスにおいても地域の民話や神話などから着想を得て、ユニークな造形へと昇華させてくれそうな期待が持てる。(2015年度ゲストキュレーター 飯田志保子)
オープンスタジオに寄せて
アンガワン・クスノがこのたびスタジオ内に仮設した「Lost and Found and Lost and What Department (LFLW:失くして見つけて失くしてそれからどうなる課)」は、オープンスタジオ期間中の日中だけ開設する架空の施設である。彼が守谷市民に依頼した秘密の質問状に寄せられた匿名の回答、戦争体験についての対面インタヴュー、そして戦後日本の状況や地域史に関する調査を基にしたこの施設は、クスノが滞在中に収集した個人史の集積で出来ている。彼は滞在当初から率直に、戦後から現在に至る日本社会と政治状況の変化や、大きな転換期を経た現代人の問題意識の所在といった、答えるのが難しい大きな問いを周囲に投げかけてきた。根底には、翻って自国インドネシアが抱える植民地時代の空白と戦後の近代史を日本と比較し、グローバルな文脈で相対化して考察しようとするクスノの関心が垣間見える。タイトルの《何を覚えていたか忘れた》は、私たちが「過去をすぐに忘れる」ことに由来している。だがLFLWはそれを批判するのでもジャーナリスティックに提示するのでもなく、クスノの感性と遊び心に彩られた徹頭徹尾フィクショナルな場として、語られなかった記憶を共有するために作られた。そこには歴史の隙間からフィクションを生み出すクスノのアーティスティックな手腕が発揮されている。(2015年度ゲストキュレーター 飯田志保子)
ステファニー・ビックフォード=スミスStephanie Bickford-Smith
英国

1989年英国・ヘルストン生まれ、ハートフォードシャー在住。 2014年ロイヤル・カレッジ・オブ・アートにてデザイン・インタラクションの修士課程を修了。主な展覧会に「Always Print The Myth」(ヴィクトリア・アンド・アルバート美術館、ロンドン、2015)、 「THE PARTY」( ヴィラ クローチェ現代美術館、ジェノヴァ、イタリア、2014)、「Buy Buy Buy, Sell」( ロイヤル・カレッジ・オブ・アート、ロンドン、2014)などがある。
人が労働や雇用の機会を通して現代社会のなかで役割を模索することや、ある理想へ近づくことの困難さを主題にパフォーマンスや映像作品を制作している。インタヴュー、自撮り、行動パターンの分析・図式化、収集物の分類・展示といった手法を用い、自らホテルの客室清掃員になって覆面調査を行うなど、理想と現実の間のジレンマに対峙しながら実体験を物語る。社会に横たわる道徳的・倫理的な境界に挑みつつ、ユーモラスな映像が特徴的な若手アーティスト。
活動の様子

Set the studio for the workshop
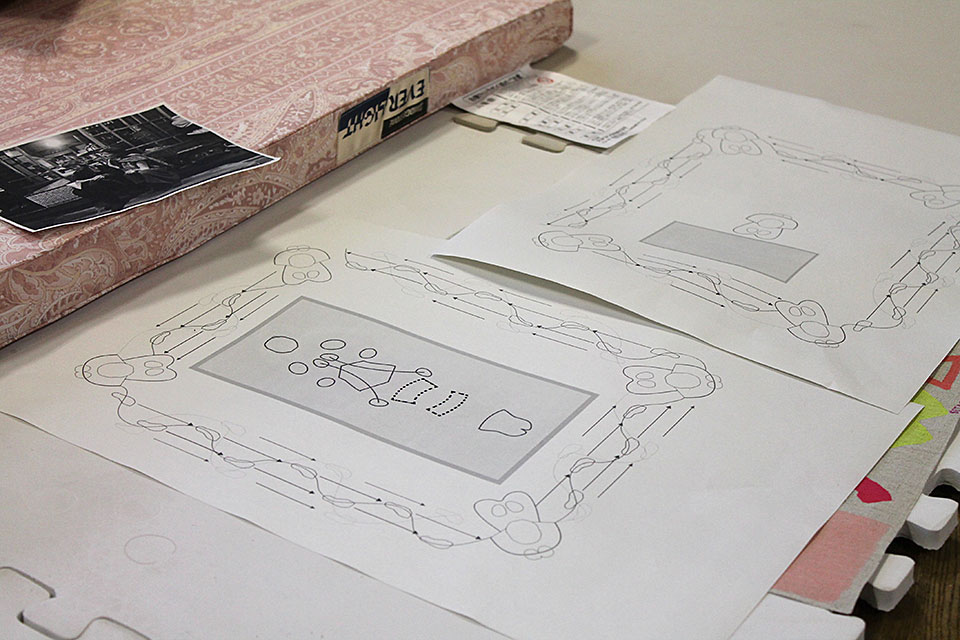
Drawing plan for the installation

Production with work partner

Kids experiencing the installation
オープンスタジオ

Perhaps I speak look feel Japanese
3-channel video installation

Still from Perhaps I speak look feel Japanese

アーティスト・ステイトメント
《たぶん、私は日本語を話す、日本人に見える、日本人として感じた》
英国ではなく、守谷で生まれ育ったとした場合、私の人格はどれほど異なったのだろうか。私自身が日本人であると想像することから、どのように1人の人間が、異なる国籍をもつ仲間と感情のつながりを持てるのか探求しています。
コミュニティに介入し、観察することで、守谷での仲間の感情を理解し始めました。この感情と私自身の守谷での体験を比較しながら、日本人としての私はどうであるかを想像し始めました。書くこと、うごき、音、パフォーマンスを通して、私自身と他者が、それぞれ別人格をイメージすることが可能となる創造的な演習を行いました。
大規模な移民社会のなかで、国籍を維持する心理的な境界に挑戦し探求しようとしています。
制作の一部として、パブロ・ナルーダによる「衣服への歌」を独唱します。
選考理由
素性と制作目的を隠してロンドン市内のフードデリバリー業やホテルの客室清掃員として2か月間働く間に撮影した映像を基に制作された《Opportunities in the Margins(周縁にある可能性)》(2014)の完成度が高く、見る者を魅了する力があった。他の映像作品も一見、体当たりのユーモラスな自撮り系ドキュメンタリーやリアリティTVのような様相を呈しているが、しっかりした方法論を持ち、自身をとりまく社会環境を客観的に観察・分析していることが伝わってくる。他者を理解することや環境に順応することの困難と不可能性を前提とし、大真面目に取り組みながらも、結果的にユーモアに転化される軽妙な作風に好感が持てる。アーカスでは「日本人になる」ためのリサーチを行う提案をしており、どのような展開を迎えるのか楽しみである。(2015年度ゲストキュレーター 飯田志保子)
オープンスタジオに寄せて
「日本人になる」ためのリサーチを行いたいという興味深い提案をしてきたビッグフォード=スミス。まずはドローイングや写真を用いて自分と周囲の人々の外観ならびに内観的な観察を重ねた。そのうえで彼女は、自分と呼応するような立場の日本人として守谷在住か出身の同年代の女性を募集し、瞑想的なワークショップを実施。プライヴェートな部屋のようなセッティングをしたスタジオ空間に参加者を招き入れ、簡単なエクササイズをしながら自分の体の部位や動きに意識を集中するよう促した。そして参加者が互いの動作を模倣し合う時間を共有した後、どこか知らない場所にいる外国人女性の気持ちになることについての問いかけをした。それによって参加者は自意識を外部に投影し、「他者になる」過程を共有した。ビッグフォード=スミスがこのワークショップで試みたのは、アイデンティティを形づくる人間の心理作用に揺さぶりをかけることである。自分の内に形成されていくかもしれない日本人のような気持ちとはどのようなものか、彼女はイギリス人としての自我を一時的に潜め、ここ守谷で感情を他者に同化させるプロセスを可視化させることに挑戦している。それは古着に袖を通し、衣服が留めているかもしれない誰かの肌と記憶の痕跡を想像することにも似ているだろう。(2015年度ゲストキュレーター 飯田志保子)
エドゥアルド・カシューシュEduardo Cachucho
南アフリカ

1985年南アフリカ・バンダービールパーク生まれ、ベルギー在住。2008年ウィットウォーターズランド大学 (ヨハネスブルグ)で建築の修士号を取得。2015年ダッチ・アート・インスティテュート(アーネム)にて美術修士課程を修了。主な活動として「GIPCA Live Arts Festival」(Gordon Institute for Performing and Creative Arts、ケープタウン大学、南アフリカ、2014)、「BORG2014, Biennial event for contemporary」 (アントワープ、ベルギー、2014)がある。また2012年には第13回ヴェネツィア・ビエンナーレ国際建築展(イタリア、2012)でアメリカ館のグループ展「Spontaneous Interventions」に携帯電話用のアプリケーション作品で参加。2011年にチッタデラルテ・ファウンダチオーネ・ピストレット(イタリア)、2015年にCSAV – Artists Research Laboratory(アントニオ・ラッティ財団、イタリア)のレジデンスプログラムに参加。植民地時代を経た南アフリカの過去と現在、そこにもたらされた言語や教育システムに対する関心を立脚点に、長期的なリサーチ・プロジェクトや映像作品の制作、また映像を伴いカシューシュ自身が登壇するレクチャー・パフォーマンスを行っている。
活動の様子

2nd workshop at Escola Opçao in Joso City

Workshop with students from Toride Shoyo High School

Meeting just before the performance

Workshop with students from the two schools
オープンスタジオ

segurando, andando, caindo – holding, walking, falling
Performance
[Performers] Abe Hiroyo, Ueno Fernando, Sakai Izumi, Sakamoto Emilly Mayumi Mota, Tazoe Rodrigo, Watanabe Natsumi


segurando, andando, caindo – holding, walking, falling
Video, 9’45”
アーティスト・ステイトメント
《segurando, andando, caindo – つかむ、歩く、倒れる》
《segurando, andando, caindo – つかむ、歩く、倒れる》は茨城の中高生2つのグループを対象に行ったワークショップのシリーズです。常総市にあるエスコーラ・オプションの日系ブラジル人中高生、また取手市の取手松陽高等学校の日本人高校生に参加してもらい、文化、言語、日常生活での身体の動きについて問いかけました。
このワークショップを実施するにあたり、私は1世紀以上にも及ぶブラジルと日本の政治的、社会的関係性を念頭に置き続けてきました。ブラジルにはおよそ1500万人の日系人が住んでおり、日本には約20万人の日系ブラジル人が住んでいます。このコミュニティと日本との関係性は、日本人でもありブラジル人でもあると自覚する人々にとって、重要なつながりとなっています。
複数回にわたって実施したワークショップからそれぞれの生徒が制作したのぼりや、そのワークショップのプロセスの様子を記録した映像で構成されたインスタレーションで成果を可視化しました。また22日の最終日には、それぞれの学校から選出した生徒たちによるパフォーマンスを行います。
選考理由
近作のうち目を奪われる作品がいくつかあった。着目点、映像の視覚的力強さ、ナラティヴを生み出す力、レクチャー・パフォーマンスの技術いずれにも長けている。南アフリカのポストコロニアルな現状から、人々の思考の中断に対する考察まで幅広い関心を持ちつつ、作品化する際にはある固有の歴史や心理メカニズムに焦点を当てて明晰に表現する力がある。また、アウトプットが教義的な態度にならず、観客を惹きつける作品になっている点も評価した。高い将来性を感じさせる若手アーティストであり、プロポーザルにあった日本におけるブラジル移民の減少についてどのようにリサーチを行い制作に結び付けていくか見てみたい。アーカスが招聘したことのない国の出身であることも考慮した。(2015年度ゲストキュレーター 飯田志保子)
オープンスタジオに寄せて
南アフリカ出身で現在ベルギーを拠点に活動するカシューシュは、これまでも異文化の流入や他者との出会いが人の心理、言語、無意識的な身体の振る舞いにどのような影響を及ぼすか、映像やパフォーマンスを用いて考察してきた。来日前からカシューシュは日本とブラジルの関係に関心を寄せていたが、茨城県常総市にあるブラジル人学校の先生との出会いから、その15-16歳の生徒と取手市の高校に通う日本人の学生を通じた、異文化間の相互関係を探求する方向へと活動を進展させてきた。11月22日に行われるパフォーマンスで両校の生徒が出会う前に、カシューシュは各校の生徒に対して別々に複数回行わたってワークショップを行った。それは彼がダッチ・アート・インスティテュートの修了制作で自ら行ったレクチャー・パフォーマンス《私はつかむ、歩く、倒れる(I’m holding, walking, falling)》(2015)を出発点とし、複数の生徒が関われるように展開したものである。文化背景を異にする他者同士が即興的に共通言語を発案・構築していく行為や、他人の日常的な仕草を注視して抽出することは、今回参加した生徒たちが常陸大宮市の「西の内和紙」を用いて制作したバナーと、それを使ってオープンスタジオ最終日に行われるパフォーマンスに反映される。カシューシュのアーカスでの活動には、相互関係によって発明されるコミュニケーションの即興性と、自分の身体がいかにしてそれを体得し、日常化するかの挑戦が凝縮されている。(2015年度ゲストキュレーター 飯田志保子)