Artist in Residence Programアーティスト・イン・レジデンスプログラム
2019 レジデント・アーティスト
今年は、海外88か国・地域から642件、国内から23件の応募がありました。厳選なる審査の結果、クリストファー・ボーリガード(イタリア)、渡邊 拓也(日本)、ルース・ウォーターズ(英国)を選出しました。3名のアーティストは、9月4日から12月12日までの100日間、茨城県守谷市のアーカススタジオで滞在制作を行います。
審査は竹久侑氏(水戸芸術館現代美術センター 主任学芸員)、田坂博子氏(東京都写真美術館 学芸員)をお招きし、アーカスプロジェクト実行委員会との協議のもと行いました。
2019年度の選考結果について
2019年度から国内アーティストの募集枠を1枠再導入し、海外のアーティストを2人、国内1人を受け入れることにした。海外からの応募については、ヨーロッパやアジアからの応募数が例年と同じくらいであったが、アフリカ大陸の国々からの応募数が飛躍的に伸びた。また国内のアーティストは、すでに美術館などでの展覧会に出品している実力の備わった人から美大での課程を修了したばかりでこれから作品の核を構築してゆく人まで、さまざまなキャリアのアーティストからの応募があった。最終審査の対象になったのは、思考と制作態度が一貫していながら、アーカスプロジェクトに滞在する積極的で具体的な動機があり、自ら設定した新たな課題に取り組む姿勢がみられるアーティストであった。そのなかでも、「引きこもり」や「禅」、「侘び寂び」、「郊外」といった多くの応募者が掲げる制作モチーフやテーマとは異なる、独自の視点や思考で提案をしているアーティストを選んだ。
小澤慶介(アーカスプロジェクト ディレクター)
クリストファー・ボーリガードChristopher Beauregard
イタリア/米国

1981年アメリカ、アイダホ州生まれ。現在 ベルギー、ブリュッセル在住。カーネギーメロン大学にてファインアートを学んだ。ボーリガードは、労働と余暇の関係に関心を持ち、主にオブジェを用いたインスタレーション作品を制作している。都市の構造と人間の行動を観察しながら、労働によって編み込まれる日常とその空隙に生まれる遊びの関係を、有機物と無機物また質感の異なる素材を 組み合わせることによって軽やかに浮かび上がらせる。
https://christopherbeauregard.com
活動の様子

Shooting at Kashima Soccer Stadium


Interview with architectural historian Hidenobu Jinnai

Site visit to Central Breakwater Outer Landfill Site
オープンスタジオ

Half Empty Time


アーティスト・ステイトメント
《半分空虚な時間》
夏季オリンピックを主催するにあたり、東京は同じ歴史を繰り返すのか?この問いをこの三ヵ月にも及ぶリサーチの基点としたが、そのほかの全ての出発点と同じように、ここから飛び立つことによってのみ、帰り道が分るとういうものだ。
今回のオリンピックを含めると、東京は三回のオリンピック・イベントの場となる:開催されなかった1940年の東京オリンピック、1964年に開催された東京オリンピック、そして2020年に開催予定の東京オリンピック。三つの歴史であり、また一つの歴史でもある。過去というものは時として非常にわかりにくいものだ。
日本橋をリサーチの拠点としたが、それは日本橋が歴史的にも日本の地理的中心であり、また二本の橋が同じ空間をありえないようなかたちで占有する、一時的かつ空間的な破断点(江戸時代に作られた運河に架かる日本橋の上を、1964年に建設された高速道路が横断している)となっているからである。ここでは加速された人の流れと物憂げな運河の衰退が重なり合う。運河の気だるい流れにこのリサーチを委ねることにより、2020年東京オリンピックの選手村のある人工島(不動産価値の高騰が見込まれる再領土化された区画)に辿り着いた。
この一時的なスタジオに何をもたらし、何を残していくのか考えてきた。ここは過渡的な空間であり、ここは私がこの場所にやって来る前の時間と、この場所を過ぎ去った後を繋ぐ橋である。そしてここで、私が現在と呼ぶ、定点、中心を見つけた。
選考理由
彼は、2020年のオリンピック・パラリンピックによって変化する東京を、過去に同様の経験をしたバルセロナやロンドン、さらに50余年以上前の東京と比較をしながら調査する。いずれの都市にもオリンピック・パラリンピック時に建てられ、現在は使われていなかったり取り壊されたりしている建築物がある。またそれが与えたコミュニティへの影響についても調査し、インスタレーションとして発表する予定だ。世界が注目するイベントを構造的に分析しつつ詩的に表す方法論に期待ができる。
オープンスタジオに寄せて
ボーリガードは、さまざまな街を訪れ、余暇と労働をテーマに、オブジェや写真、映像などを組み合わせて作品を制作しています。それは、個人一人一人というより、その集合で ある社会や時代の無意識を探りあてようとする試みのように見えます。
アーカスプロジェクトの滞在において、ボーリガードは、1964年と2020年の2つの東京 オリンピックについて調べ、その間に変わってきた都市を隠喩的に表しています。制作を進めていく上で印象的だったことは、彼が直感的に、1964年に見た未来は2020年において実現しておらず、2020年の夢を1964年の高度経済成長期に見ているようだと指摘したことです。ノスタルジーに向かっている未来の東京オリンピック。これら2つのオリンピックを結ぶ素材として、循環を意味する「水」 に着目しています。1964年の東京オリンピックでは川を使って都市の交通網が整えられました。そして2020年のオリンピックでは、東京湾岸の水辺に競技会場が整備されています。スタジオには、日本橋川などを取材した 映像と地元の陶芸家に提供してもらった甕(かめ)が配置されています。甕には小さなカーブミラーがついていて、覗き込むと守谷市内やカシマサッカースタジアムにおいて集められた水が溜まっています。互いに背を向けたミラーは、過去から未来また未来から過去を見 ることの隠喩になっていて、水を巡って過去と未来が交わる現在地を表しているようにも見えます。(ディレクター 小澤慶介)
渡邊 拓也Takuya Watanabe
日本

Photo: TU-TIMA
1990年東京生まれ、在住。東京藝術大学大学院美術研究科先端芸術表現専攻修了。調査や聞き取りを通して出会ったある個人の境遇を取り上げながら、逆説的に社会の構造や力を明かすような映像インスタレーションを制作している。もともと陶芸をやっていた渡邊だが、ある時訪れた陶器のタイル工場で目にした工員の単純作業に着想を得て制作した、労働をテーマにした作品《工員K》、また、兄弟の関係と家庭内暴力を巡る出来事をモチーフに、郊外や家族をテーマにした作品《弟の見ていたもの》などをこれまでに発表してきた。
活動の様子

Interview with Yoshihiro Yokota [Ibaraki NPO Center・Commons]

Interview at a cafe in Joso City


Interview with Yuso Kiriki
オープンスタジオ

Good luck on your journey
Single channel video, 24′30′′, 2019
Installation view

Still from Good luck on your journey
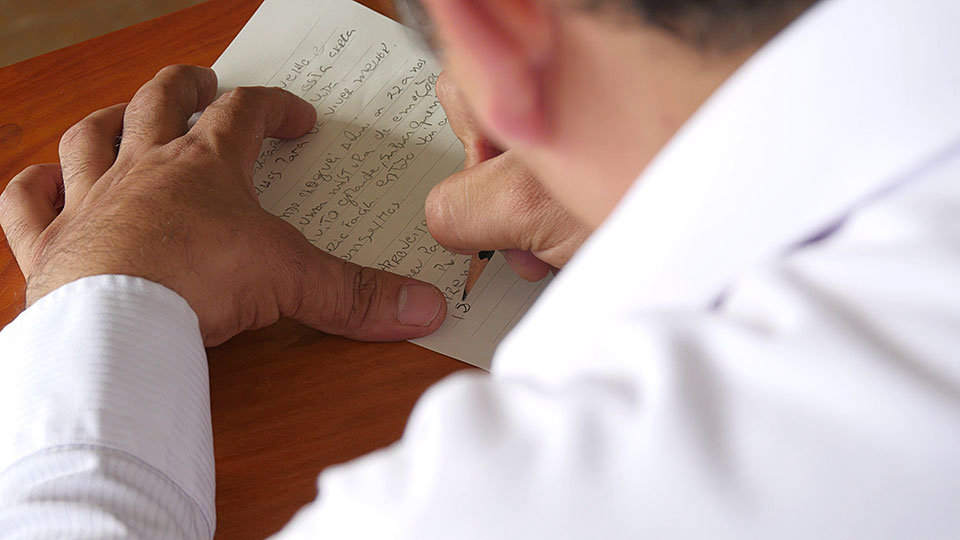
Still from Good luck on your journey
アーティスト・ステイトメント
《Good luck on your journey》
いかにして他の誰かの見ている世界を知ることができるか、またそれを表象することができるか。これは私の制作における大きな課題です。アーカスプロジェクトでの滞在では、「他の誰か」として常総市に住む日系ブラジル人にフォーカスをあてました。彼らは、日本とブラジルにおける文化的、政治的、言語的な違いの中で複雑なアイデンティティを持ちます。
《Good luck on your journey》という映像作品は、人生の前半をブラジル、後半を日本で過ごしてきた日系ブラジル人男性と、日本で生まれ育った彼の息子との出会いを契機とし、彼らとともに制作しています。この男性はよくステレオタイプな日本人のようにふるまいます。日本語での日常会話や慣例的な挨拶を身につけている一方で、複雑なことや感情が伴うことは日本語で伝えることができないと言います。私はまずこの男性に、日本へ旅立つ前の過去の自分に手紙を書くことを提案しました。そして、ポルトガル語で書かれたその手紙を、当時の彼と同年代の息子が受け取り、息子は手紙を日本語へ翻訳します。日本語に訳された手紙を、息子の協力をうけながら、男性が日本語で語り直す過程をとらえたのが今回の映像作品です。手紙には、この男性が見た日本社会と、これから希望を持って日本へ働きに来ようとしている若者への励ましの言葉が綴られています。
選考理由
アーカスプロジェクトでは、守谷市のとなりの常総市での、日系ブラジル人コミュニティと日本人社会との分断に着目し、調査を経て作品を構築する。2015年の夏に起きた関東・東北豪雨は常総市を流れる鬼怒川の堤防を決壊させ、非常時における人々の協働を生んだ一方で、その災害情報の伝達を巡ってはコミュニティの分断も明らかになった。当時の心理や感情について当事者への聞き取りや現場での調査を行う予定だ。自然災害や移民、労働などをテーマに現代の日本の社会を捉えなおす試みに期待が持てる。
オープンスタジオに寄せて
渡邊は、ある特定の個人が向き合っている現実から、より大きな社会の仕組みや力のあり方を、映像インスタレーションで描き出します。これまでに、大きな工場で働く工員に聞き取りをして制作した《工員K》や、大都市の郊外で暮らす一家の破局の物語を語り直した《弟の見ていたもの》などを発表しています。
アーカスプロジェクトでの滞在では、守谷市の隣の常総市に住む日系ブラジル人コミュニティへ赴き、彼らと地元の日本人社会との関わりを調べることから作品を構想しました。そこで出会ったのがユウゾウさん。22歳の時に故郷のブラジルを離れて来日し、今年で来日21年目になるそうです。話をしてゆくうちに、渡邊は、彼が社会生活では日本語を、細やかな感情を表現するにはポルトガル語を使っていることに気づきます。それは、彼のアイデンティティ(自己同一性)が2つの言語文化の間で引き裂かれているようであったとも言います。
オープンスタジオにおいて、渡邊は、そうしたユウゾウさんが、ブラジルを旅立つ21年前の自分に向けてポルトガル語で書いたメッセージをもとに映像インスタレーションを展開しています。登場人物はユウゾウさんともう 一人、彼の息子であるガブリエルさん。ポルトガル語と日本語を自在に操る息子が手紙を翻訳し、ユウゾウさんがそれを日本語で読み上げる時、常総市に埋め込まれている薄くとも確実に存在する日系ブラジル人の文化政治的な一つの層が浮かび上がってくるようです。(ディレクター 小澤慶介)
ルース・ウォーターズRuth Waters
英国

Photo: Soohyun Choi
1986年イギリス、ランカスター生まれ。現在はロンドンを拠点に活動している。ゴールドスミスカレッジにてファインアートを学んだ。ウォーターズは、高度にネットワーク化された現代において、過密になるコミュニケーションが現代に生きる人々に及ぼす「不安」に関心を寄せている。インターネット上の資料の調査や当事者への聞き取りなどをもとに自ら脚本を書き、セットを設え、撮影し、映像インスタレーションとして発表する。
活動の様子

Interview with psychologist Yu Urata

Interview with astronaut Naoko Yamazaki

Visit to Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA)

オープンスタジオ

Swallow Up
Single channel video, 8′, 2019
Installation view

Still from Swallow Up

Still from Swallow Up
アーティスト・ステイトメント
《Swallow Up》
宇宙飛行士が宇宙から見た地球の景色に関し、すでに多くのことが語られてきた。そこでは人為的に作られた国境や地球の存在のはかなさがさらけ出され、それまでの考え方が一変するような体験だと言われている。しかしそう遠くない未来において、これは飛行機からの景色と同じくらい身近なものとなるだろう。
そのとき、(地球が見える窓とは)反対側の窓から見える深宇宙の景色とは何なのだろう。この景色が人間の考え方をどのように変えるのだろう?今回の滞在制作では、無限や宇宙空間がどのように人間の精神に影響を及ぼすのかをリサーチしてきた。木下冨雄1さんには無限の暗闇と微小重力に関するお話を、山崎直子2さんからはISS(国際宇宙ステーション)の窓から見える景色に何を感じたのか、また浦田悠3さんには地上における大きな実存的な問題に我々がどのように向き合い、理解できるのかを伺った。宇宙空間を理解しようと試みることで、私たちの日常の在り方が意図的に作り上げられたものであることに気づき、新たな日常の在り方を想像する契機になるのではないかということに、私は関心を寄せている。
1 京都大学名誉教授である木下冨雄は、2005年にJAXAと共同で人文・社会科学からの宇宙開発の研究を行った。
2 山崎直子はJAXA所属時に宇宙飛行士として、スペースシャトル・ディスカバリー(STS-131)のミッションで宇宙に行った。
3 大阪大学の研究者である浦田悠は、「人生の意味」を研究対象としている。
選考理由
彼女は、人間のエゴと宇宙開発について調査をする予定。後期資本主義社会において、人類が未だ到達していない領域を切り開いてゆく意思と行動は一体何に支配されているのかという問いに向き合う。人間はいつ宇宙を意識するのか、またそうした宇宙空間と資本主義との関係はどのようなものであるのかを、関係者や専門家に聞き取りを行い、映像として発表する。世界(資本主義)と宇宙空間の関係を守谷から考えるという視点は注目に値する。
オープンスタジオに寄せて
ウォーターズは、経済の成長を目指す資本主義の社会が人々にもたらす不安に着目し、主に映像インスタレーション作品を制作しています。実際にマインドフルネスのセラピーで使われている言葉や方法、空間を作品に取り入れながら、社会における人間の心理を巧みに描き出します。
ウォーターズがアーカスプロジェクトの滞在中に取り組んだことは、宇宙空間における人間の認識や心理の変化を探ることです。しばしば宇宙飛行士たちが経験する概観効果 (overview effect)は、宇宙から地球全体を見る経験に起因する認識的・心理的変化ですが、人間は地球全体を見渡すことができると、悩みや諍いの無意味を感じるようになるとのこと。ところが、宇宙心理学の研究者に取材をしたところ、地球の姿が見えなくなって全くの暗闇になってしまう宇宙空間では、人は自らの存在の意義を把握することが困難であることを知ることになります。いずれにしても、彼女は、人間が宇宙空間について理解を深めたならば、資本主義によって形づくられる日々を絶対視することはなくなるのではないかと思うに至りました。
暗くしたスタジオでは、宇宙の空間について語る宇宙飛行士や宇宙心理学研究者などのインタビュー映像が投影されています。宇宙は不安から人間を解き放つのか、あるいは人間をさらなる別の不安の渦に巻き込んでゆくのか。資本と不安をめぐる問いはつづいてゆきます。(ディレクター 小澤慶介)